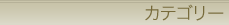ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)
社長業を極めるためのカリキュラムについて、「日本的経営のリニューアル」という視点から紹介します
- トップページ
- ブログ個人トップ
前ページ
次ページ
2008年03月28日(金)更新
立案力と遂行力
●ある日のことです。世界的カメラメーカーで15年間修業し、最近になって父親が経営するK精密に入社したK専務が相談に来られました。
●内容は社員のレベルが違いすぎるため、今まで経験してきたことの大半が役に立たないということでした。K氏が以前勤めていたのは一部上場企業であったため、社員教育制度も充実し、ビジネススキルやコミュニケーション能力もあるエリートが入社してくる会社でした。
●しかし、K精密は社員数約30名の部品メーカーで、社員全員が中途採用。それも、全員が基礎研修などを受けたことがあるわけではなく、中には職人気質の現場社員やコミュニケーションを満足に取れないスタッフもいるとのことでした。
●K氏はこう嘆いていました。「武沢さん、私が前の会社で培ってきたやり方が通用しないんですよ。前職では、大まかな方向性さえ指示しておけば、部下が自分で目標や行動計画を設定して動いてくれました。でも今いる会社では、方向性を示すだけでは足りず、具体的な作業指示も出してやらないと社員が動かないのです」
●K氏が前職と現職のギャップに悩み、嘆く気持ちもわからないではありませんが、嘆いていても始まりません。
●大企業は人員も多く、社員の質も粒ぞろいなので「私は決定する人、あなたは実行する人」というように、役割分担ができます。しかし、中小零細企業の経営者は、決定するだけではなく、現場の陣頭指揮もとれる人でなければならないのです。その意味でいうと、中小企業の経営者は、大企業の経営者より有能な人材でなければ務まらないのです。
●経営力とは「立案力」と「遂行力」の和のことです。中小企業を経営するには、社員のレベルの低さを嘆く前にまず、自分の立案力と遂行力の向上をはかりましょう。ついでにそのとき、「すべての責任は我にあり」くらいに考えた方が、精神的なストレスも少なくなるでしょう。
●内容は社員のレベルが違いすぎるため、今まで経験してきたことの大半が役に立たないということでした。K氏が以前勤めていたのは一部上場企業であったため、社員教育制度も充実し、ビジネススキルやコミュニケーション能力もあるエリートが入社してくる会社でした。
●しかし、K精密は社員数約30名の部品メーカーで、社員全員が中途採用。それも、全員が基礎研修などを受けたことがあるわけではなく、中には職人気質の現場社員やコミュニケーションを満足に取れないスタッフもいるとのことでした。
●K氏はこう嘆いていました。「武沢さん、私が前の会社で培ってきたやり方が通用しないんですよ。前職では、大まかな方向性さえ指示しておけば、部下が自分で目標や行動計画を設定して動いてくれました。でも今いる会社では、方向性を示すだけでは足りず、具体的な作業指示も出してやらないと社員が動かないのです」
●K氏が前職と現職のギャップに悩み、嘆く気持ちもわからないではありませんが、嘆いていても始まりません。
●大企業は人員も多く、社員の質も粒ぞろいなので「私は決定する人、あなたは実行する人」というように、役割分担ができます。しかし、中小零細企業の経営者は、決定するだけではなく、現場の陣頭指揮もとれる人でなければならないのです。その意味でいうと、中小企業の経営者は、大企業の経営者より有能な人材でなければ務まらないのです。
●経営力とは「立案力」と「遂行力」の和のことです。中小企業を経営するには、社員のレベルの低さを嘆く前にまず、自分の立案力と遂行力の向上をはかりましょう。ついでにそのとき、「すべての責任は我にあり」くらいに考えた方が、精神的なストレスも少なくなるでしょう。
2008年02月29日(金)更新
ギュッと締める力
●最近、「重役」という意味合いでよく使われている「エグゼクティブ(executive)」という言葉がありますが、これはエグゼキュート(execute)が語源といわれています。executeとは、「実行する・遂行する」という意味のほか、(刑を)執行するとか、(ニワトリなどを)ギュッと締める、という意味でも使われます。
●ですから本来のエグゼクティブとは、まさに「実行する人」であり、部下を「ギュッと締める」ことができる人なのです。会社組織で誰よりも実行力を要求されるという点において、頂点に立つのが社長であることは、言わずもがなでしょう。
●親鸞がまだ松若丸と呼ばれていた9歳のとき、慈円和尚に弟子入り志願したものの断られ、次のような歌を詠みました。
「明日ありと 思ふ心の あだ桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは」
「今この瞬間に事をなし遂げないと、明日があるという保証は何もないんだ」、という若き親鸞の緊張感が伝わってくる名句ではないでしょうか。
●会社経営にとって「明日はない」という緊張感は大切です。実際には明日も明後日もあるでしょうが、「明日」と「今日考えている明日」は同じではなく、「来年」は「今と同じ環境の来年」ではありません。経営はいつも「今」しかないのです。
●たとえば、「5か年経営ビジョン」を作ったら、その達成の命運は今期、いや今月にかかっているんだ、という気迫を大切にしなければなりません。そうした会社だけが長期ビジョンを実現できるのです。これは、ギュッと締める人が社内にいるからです。
●新しいことに挑戦しようとすると、面白いアイデアはどこの会社でもでてきます。ところが、そこで締める力がないと、アイデアを実行に移せません。往々にして、「そういえば、あの件どうなったの?」「さあ、どうでしょう…」と中途半端になってしまい、はたしてアイデアが良かったのか悪かったのか、評価不能になってしまいます。
●逆に、社内をギュッと締める力がある会社では曖昧なことは起こりません。これは、「しつけ」の差です。リーダーに組織を締めるだけの力があれば、部下もおのずと引き締まった仕事をするのです。
●これからは、エグゼクティブとか重役という単語を聞くたびに「ギュッと締める力」の重要性を思い出していきたいものです。
●ですから本来のエグゼクティブとは、まさに「実行する人」であり、部下を「ギュッと締める」ことができる人なのです。会社組織で誰よりも実行力を要求されるという点において、頂点に立つのが社長であることは、言わずもがなでしょう。
●親鸞がまだ松若丸と呼ばれていた9歳のとき、慈円和尚に弟子入り志願したものの断られ、次のような歌を詠みました。
「明日ありと 思ふ心の あだ桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは」
「今この瞬間に事をなし遂げないと、明日があるという保証は何もないんだ」、という若き親鸞の緊張感が伝わってくる名句ではないでしょうか。
●会社経営にとって「明日はない」という緊張感は大切です。実際には明日も明後日もあるでしょうが、「明日」と「今日考えている明日」は同じではなく、「来年」は「今と同じ環境の来年」ではありません。経営はいつも「今」しかないのです。
●たとえば、「5か年経営ビジョン」を作ったら、その達成の命運は今期、いや今月にかかっているんだ、という気迫を大切にしなければなりません。そうした会社だけが長期ビジョンを実現できるのです。これは、ギュッと締める人が社内にいるからです。
●新しいことに挑戦しようとすると、面白いアイデアはどこの会社でもでてきます。ところが、そこで締める力がないと、アイデアを実行に移せません。往々にして、「そういえば、あの件どうなったの?」「さあ、どうでしょう…」と中途半端になってしまい、はたしてアイデアが良かったのか悪かったのか、評価不能になってしまいます。
●逆に、社内をギュッと締める力がある会社では曖昧なことは起こりません。これは、「しつけ」の差です。リーダーに組織を締めるだけの力があれば、部下もおのずと引き締まった仕事をするのです。
●これからは、エグゼクティブとか重役という単語を聞くたびに「ギュッと締める力」の重要性を思い出していきたいものです。
2008年02月15日(金)更新
困ったらあかん
●東京に本社のある松下電送(現・パナソニック コミュニケーションズ)がファクシミリをつくり始めた頃の話です。社長の木野親之氏が松下幸之助氏から呼ばれて、大阪の門真にある松下電器本社をたずねました。
●そして幸之助翁に「君、何か困ったことはあるか?」と問われ、木野氏はとっさに「はい、問題はいろいろありますが頑張っています」と答えたそうです。
●そうしたやりとりの後、幸之助翁は最後に「困っても困ったらあかんで」と言われたそうです。それを聞いた木野社長は、帰りの飛行機のなかで心が晴ればれとして、やる気がみなぎってきたとか。
●このやりとり自体は禅問答のようなものだと思います。しかし、ファクシミリという新しい商品を世に送り出し、事業として軌道に乗せることは、決して容易なことではなかったはずです。新規商品の開発につきものの問題があちこちで発生し、困ったことばかりだったのでしょう。
●当然そのことは、幸之助翁も知り抜いていたはず。その上で翁はこう言いたかったのではないでしょうか。
「困るような事はいっぱいあるやろうが、しかしそれは外的なことや。けど、そのせいで君の心までもが困ったらあかんのや」と。
木野社長をわざわざ来阪させたのは、そのメッセージを伝えるためだったのかもしれません。
●また、幸之助翁は別の場所でこんなことも語っています。
「心配するのが社長の仕事や。社長が心配するのが嫌になってしまったら、それは社長を辞めるときや」
心配し、心まで困り果てるのが社長の仕事。ナンバー2以下はその必要なしということでしょう。トップらしい、潔い心意気ではないでしょうか。
●そして幸之助翁に「君、何か困ったことはあるか?」と問われ、木野氏はとっさに「はい、問題はいろいろありますが頑張っています」と答えたそうです。
●そうしたやりとりの後、幸之助翁は最後に「困っても困ったらあかんで」と言われたそうです。それを聞いた木野社長は、帰りの飛行機のなかで心が晴ればれとして、やる気がみなぎってきたとか。
●このやりとり自体は禅問答のようなものだと思います。しかし、ファクシミリという新しい商品を世に送り出し、事業として軌道に乗せることは、決して容易なことではなかったはずです。新規商品の開発につきものの問題があちこちで発生し、困ったことばかりだったのでしょう。
●当然そのことは、幸之助翁も知り抜いていたはず。その上で翁はこう言いたかったのではないでしょうか。
「困るような事はいっぱいあるやろうが、しかしそれは外的なことや。けど、そのせいで君の心までもが困ったらあかんのや」と。
木野社長をわざわざ来阪させたのは、そのメッセージを伝えるためだったのかもしれません。
●また、幸之助翁は別の場所でこんなことも語っています。
「心配するのが社長の仕事や。社長が心配するのが嫌になってしまったら、それは社長を辞めるときや」
心配し、心まで困り果てるのが社長の仕事。ナンバー2以下はその必要なしということでしょう。トップらしい、潔い心意気ではないでしょうか。
2008年02月08日(金)更新
間接的リーダーシップ
●ある学習塾の社長の話です。彼は毎日毎日、何時間も生徒の送迎バスの運転をしていました。
●「こんな大切な仕事を部下に任せるわけにはいかない」というのがその理由です。そのうち、この学習塾が地域で評判になり、生徒数がついに500名を超える規模になっても、彼はハンドルを離しませんでした。
●もちろん仕事は送迎だけではありません。授業も教えていることからフル稼働の日が続き、しまいには糖尿病が原因の高血圧で入院までしてしまい、事業を縮小せざるをえなくなりました。
●会社は社長の器より大きくならないといいます。例外的に大きくなってしまう場合もあるでしょうが、長いスパンでみれば社長の器以上にはなりません。ですから社長は、会社を経営しながら自らの器を広げていかねばならないのです。そこで、社長の器とはどのようにして広げていくべきなのか、三つの段階に分けて考えてみましょう。
●最初は「兵たる器」という段階です。まずは兵として優秀である状態をめざしましょう。肩書きこそ「代表取締役社長」であったとしても、現実には一人で営業活動から納品、請求書発行、代金回収、クレーム処理などすべて処理しなければなりません。だから、まず兵として優秀な状態を目指すのです。
●その次は「兵の将たる器」という段階です。従業員を採用し、社長はプレイングマネージャーとなって指揮をとりながら、率先して動きます。この段階になると、社長は「兵」としての強さだけでなく、部下を指揮して戦いに勝利できるリーダーシップを学ぶのです。
●最後は「将の将たる器」という段階。将の将、長の長として、今までとは次元が違う戦略的な仕事をこなさなければなりません。たとえば、組織の目的やビジョンを掲げることや組織づくり、人財育成に提携戦略など、明日に向けた仕事をする段階です。
●言い換えれば、兵の将をやっている時は「直接的リーダーシップ」、将の将になると「間接的リーダーシップ」が求められると言えるでしょう。
●直接的リーダーシップとは、「1+1はいくつですか?」と部下に聞かれたとき、「2」と即答してやるようなリーダーシップです。そうすることで感謝や尊敬されるでしょう。
●ところが「間接的リーダーシップ」は答えを言いません。足し算や引き算の解き方を教えたり、時計を作って見方を教えてやるのが仕事なのです。部下の誰もが「1+1=2」を解けるような教育・原則の作成、つまり社内環境の整備や方針づくりなどが求められます。それが「間接的リーダーシップ」なのです。
●直接的と間接的、どちらのリーダーシップも同じように大切です。そして経営者とは、その両方を兼ね備えていなければならないのです。
●「こんな大切な仕事を部下に任せるわけにはいかない」というのがその理由です。そのうち、この学習塾が地域で評判になり、生徒数がついに500名を超える規模になっても、彼はハンドルを離しませんでした。
●もちろん仕事は送迎だけではありません。授業も教えていることからフル稼働の日が続き、しまいには糖尿病が原因の高血圧で入院までしてしまい、事業を縮小せざるをえなくなりました。
●会社は社長の器より大きくならないといいます。例外的に大きくなってしまう場合もあるでしょうが、長いスパンでみれば社長の器以上にはなりません。ですから社長は、会社を経営しながら自らの器を広げていかねばならないのです。そこで、社長の器とはどのようにして広げていくべきなのか、三つの段階に分けて考えてみましょう。
●最初は「兵たる器」という段階です。まずは兵として優秀である状態をめざしましょう。肩書きこそ「代表取締役社長」であったとしても、現実には一人で営業活動から納品、請求書発行、代金回収、クレーム処理などすべて処理しなければなりません。だから、まず兵として優秀な状態を目指すのです。
●その次は「兵の将たる器」という段階です。従業員を採用し、社長はプレイングマネージャーとなって指揮をとりながら、率先して動きます。この段階になると、社長は「兵」としての強さだけでなく、部下を指揮して戦いに勝利できるリーダーシップを学ぶのです。
●最後は「将の将たる器」という段階。将の将、長の長として、今までとは次元が違う戦略的な仕事をこなさなければなりません。たとえば、組織の目的やビジョンを掲げることや組織づくり、人財育成に提携戦略など、明日に向けた仕事をする段階です。
●言い換えれば、兵の将をやっている時は「直接的リーダーシップ」、将の将になると「間接的リーダーシップ」が求められると言えるでしょう。
●直接的リーダーシップとは、「1+1はいくつですか?」と部下に聞かれたとき、「2」と即答してやるようなリーダーシップです。そうすることで感謝や尊敬されるでしょう。
●ところが「間接的リーダーシップ」は答えを言いません。足し算や引き算の解き方を教えたり、時計を作って見方を教えてやるのが仕事なのです。部下の誰もが「1+1=2」を解けるような教育・原則の作成、つまり社内環境の整備や方針づくりなどが求められます。それが「間接的リーダーシップ」なのです。
●直接的と間接的、どちらのリーダーシップも同じように大切です。そして経営者とは、その両方を兼ね備えていなければならないのです。
2008年01月18日(金)更新
誰を選ぶべきか
●「優秀な人材が優秀な部門にいる」。会社ではよくある話です。ですが仮に、一番優秀な人材を一番問題のある部門に異動させたら、どうなるでしょうか。
●こんな例があります。かの名著『ビジョナリー・カンパニー2』(ジェームズ・C・コリンズ著 山岡 洋一訳 日経BP社)でもたびたび対比して紹介されている、「キャメル」で有名なR・J・レイノルズ社と、「マルボロ」でおなじみのフリップ・モリス社の話です。
●両社とも世界的に有名なタバコ会社ですが、実は経営力における格差は相当あり、フィリップ・モリスのほうが格段に上のようです。
●1960年代の初頭の話です。両社ともに売上高の大部分は国内(アメリカ)事業部のみによるものでした。その頃は、R・J・レイノルズがフィリップ・モリスより勝っていたそうです。
●やがて、両社とも国際事業を展開していくことになったのですが、当時の経営陣の意思決定が未来の命運を決めることになります。
●R・J・レイノルズの経営者は、当時のビジネスウィーク誌のインタビューで「世界のどこかにいる外国人が『キャメル』を買いたいというのなら、電話をかけてくればいいんだ」と答えました。
●つまり「欲しいのなら買いに来い」という姿勢です。これはトップの発言だけにとどまりません。事実、同社はしばらくそういった経営姿勢にのっとった販売戦略を展開していました。
●一方、フィリップ・モリスのCEOだったカルマンはどうしたか。当時、まだ1%に満たない国際事業こそが長期的な成長の宝庫とみていた彼は、そのための戦略を考え続け、ついにある結論に達しました。戦略として「何をすべきか」を考えるのではなく、「責任者として誰を選ぶべきか」を決めることが、自分の役目だと気づいたのです。
●カルマンは、社内でもっとも優秀だったジョージ・ワイスマンに白羽の矢を立てました。全売上のうち99%を占める国内事業の責任者だった彼に、国際事業部を任せる決断を下したのです。
●当時の国際事業部は、名ばかりの不採算部門でした。当然、そこへの異動が決まったワイスマンは、最初は左遷だ、降格だ、と社内外で騒ぎ立てられましたが、カルマンはワイスマンを支援し続けました。
●その後、国際事業部はフィリップ・モリスでもっとも高い成長率を記録。最大規模を誇る部門になるとともに、看板商品の「マルボロ」はアメリカ国内市場よりも3年早く、世界市場で首位に立ったのです。この頃には、件の人事も「天才的なものであった」と評価されるようになりました。
●フィリップ・モリス社の話は、問題部門やお荷物整理に優秀な人材をあてるのがよい、という単純な話ではありません。今は不振でも、将来的に成長の見込みが高い部門には優秀な人材を当てるのが良い、ということです。
●社長の決断には「何をすべきか」だけではなく、「誰を選ぶべきか」もとても重要なのです。
(参考:『ビジョナリーカンパニー2』ジェームズ・C・コリンズ著 山岡 洋一訳 日経BP社)
●こんな例があります。かの名著『ビジョナリー・カンパニー2』(ジェームズ・C・コリンズ著 山岡 洋一訳 日経BP社)でもたびたび対比して紹介されている、「キャメル」で有名なR・J・レイノルズ社と、「マルボロ」でおなじみのフリップ・モリス社の話です。
●両社とも世界的に有名なタバコ会社ですが、実は経営力における格差は相当あり、フィリップ・モリスのほうが格段に上のようです。
●1960年代の初頭の話です。両社ともに売上高の大部分は国内(アメリカ)事業部のみによるものでした。その頃は、R・J・レイノルズがフィリップ・モリスより勝っていたそうです。
●やがて、両社とも国際事業を展開していくことになったのですが、当時の経営陣の意思決定が未来の命運を決めることになります。
●R・J・レイノルズの経営者は、当時のビジネスウィーク誌のインタビューで「世界のどこかにいる外国人が『キャメル』を買いたいというのなら、電話をかけてくればいいんだ」と答えました。
●つまり「欲しいのなら買いに来い」という姿勢です。これはトップの発言だけにとどまりません。事実、同社はしばらくそういった経営姿勢にのっとった販売戦略を展開していました。
●一方、フィリップ・モリスのCEOだったカルマンはどうしたか。当時、まだ1%に満たない国際事業こそが長期的な成長の宝庫とみていた彼は、そのための戦略を考え続け、ついにある結論に達しました。戦略として「何をすべきか」を考えるのではなく、「責任者として誰を選ぶべきか」を決めることが、自分の役目だと気づいたのです。
●カルマンは、社内でもっとも優秀だったジョージ・ワイスマンに白羽の矢を立てました。全売上のうち99%を占める国内事業の責任者だった彼に、国際事業部を任せる決断を下したのです。
●当時の国際事業部は、名ばかりの不採算部門でした。当然、そこへの異動が決まったワイスマンは、最初は左遷だ、降格だ、と社内外で騒ぎ立てられましたが、カルマンはワイスマンを支援し続けました。
●その後、国際事業部はフィリップ・モリスでもっとも高い成長率を記録。最大規模を誇る部門になるとともに、看板商品の「マルボロ」はアメリカ国内市場よりも3年早く、世界市場で首位に立ったのです。この頃には、件の人事も「天才的なものであった」と評価されるようになりました。
●フィリップ・モリス社の話は、問題部門やお荷物整理に優秀な人材をあてるのがよい、という単純な話ではありません。今は不振でも、将来的に成長の見込みが高い部門には優秀な人材を当てるのが良い、ということです。
●社長の決断には「何をすべきか」だけではなく、「誰を選ぶべきか」もとても重要なのです。
(参考:『ビジョナリーカンパニー2』ジェームズ・C・コリンズ著 山岡 洋一訳 日経BP社)
| «前へ | 次へ» |
 ログイン
ログイン